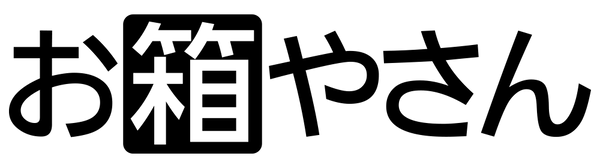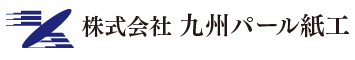こんにちは!
6月27日は「ちらし寿司の日」であるとご存じでしょうか?
時は江戸時代までさかのぼり、岡山県の郷土料理「ばら寿司」が生まれるきっかけとなった備前岡山藩主・池田光政の命日に由来しているそうです。
ちらし寿司の華やかさや美味しさは、今では全国で親しまれていますが、その誕生の裏には、意外にも「節約」や「知恵」が関係していたのです。
ちらし寿司の誕生と“倹約令”の関係
江戸時代、備前岡山藩(現在の岡山県)で大洪水が発生。
その当時の藩主であった池田光政は、災害からの復興と財政再建を目的に「一汁一菜令(いちじゅういっさいれい)」という倹約政策を打ち出しました。
この“一汁一菜令”とは、「食事はご飯と味噌汁、そしておかずは一品だけ」という厳しい制限を設けたものでした。
贅沢を慎むためのこの命令は、庶民にとっては非常に大きな制限だったことでしょう。
しかし、人々はその中でも食事を少しでも楽しく、美味しくしたいという思いを捨ててはいませんでした。
ちらし寿司は「知恵の料理」だった
倹約令の中で生まれた知恵。
それが、現在の「ちらし寿司」に通じるばら寿司です。
一品の制限を逆手にとり、たくさんの具材を“一つのおかず”としてまとめてしまう“という、まさに庶民の工夫の結晶。
例えば、煮物・焼き物・酢の物など、それぞれ本来は別々のおかずであるような素材を、すべて酢飯の上にのせて一つの料理として完成させる。
このアイデアは、食の制限を乗り越えながらも、見た目の美しさと味の多様性を兼ね備えた料理として進化を遂げ、今では祝いの席や特別な日の定番料理として定着しています。
地域ごとに呼び方も具材も多様!それがちらし寿司の魅力
このちらし寿司、実は地域によって呼び方も具材も少しずつ違います。
五目寿司
ばら寿司
混ぜ寿司
ちらし寿司
寿司飯
例えば、関東ではマグロやイクラ、エビなどを乗せた“華やか系”のちらし寿司が主流。
一方で、関西や中国地方では、椎茸・錦糸卵・かんぴょう・穴子などの煮物具材を盛りつけた“素朴で味わい深い”スタイルが好まれています。
どの地域でも共通しているのは、「特別な日や、良いことがあった日」に食べる料理としての文化があること。
節句やお祝い、おもてなしの場でもちらし寿司は大活躍してきました。
記念日を意識して食事を楽しむ
食事とは、ただ空腹を満たすためだけのものではありません。
その背景や意味、歴史を知ることで、同じ料理でもより深く、より豊かに味わうことができます。
「今日はちらし寿司の日だから、食卓にちらし寿司を出してみよう」
そんな小さなきっかけが、家族との会話を生み、日常の中に彩りを添えてくれるかもしれません。
ちらし寿司の容器は「お箱やさん」で!
そんな“ハレの日の料理”であるちらし寿司を、より美味しく・美しく・衛生的に届けるために、容器にもこだわってみませんか?
九州パール紙工では、ちらし寿司をはじめとする各種お寿司に最適な高品質の食品容器を多数取りそろえたECサイト「お箱やさん」を運営しています。
お箱やさんでは、業務用から個人利用まで対応できるさまざまなサイズ・デザイン・素材の容器を展開。
「見た目の高級感」「配送のしやすさ」「食品の鮮度保持」など、多様なニーズにお応えしています。
記念日や行事に合わせてちらし寿司を提供する飲食店様や仕出し店様、また個人のお祝いシーンにもぜひご活用ください。
▶お箱やさん 公式サイトはこちら
食の背景を知ることで、日常の一皿が特別なものに変わる
「ちらし寿司の日」をきっかけに、食文化の豊かさに触れてみてはいかがでしょうか。
そしてその美味しさをさらに引き立てる容器選びには、ぜひ、お箱やさんをご活用ください。
九州パール紙工 お箱やさんのお問い合わせ・購入はこちらから
今後もブログを通じて、製品情報や活用事例、季節ごとのおすすめ商品などを発信していきます。どうぞお楽しみに!
最新の折り箱デザインや季節に合わせた提案などをInstagramでも紹介中!